旅行業法「定義」

旅行業法「定義」
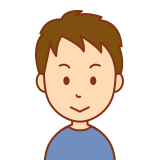
旅行業法「定義」についてみていきましょう。「定義」とは、簡単に言うと「旅行業に該当するための条件」です。それでは、何をすると旅行業になり、また、何が旅行業にならないのか、解説していきます。
旅行業とは
旅行業とは、大きく分けて以下の3つに分類される。
1.報酬を得ていること
- 旅行者や旅行サービスの宿泊・運送機関から報酬を得ること
2.一定の行為を行うこと
一定の行為とは、大まかに以下の行為を指す。
- 旅行者と運送・宿泊などのサービス提供者との間に立ち、旅行サービスを手配する業務
- 旅行者のために(依頼で)運送または宿泊のサービスの提供を受けられるように手配する業務(企画旅行、手配旅行)
- 企画旅行、手配旅行に付随する業務で、レストラン手配や遊園地などのチケットなどを手配する業務(ex. 1泊2日のツアーが提供する夕食や観光地の入場チケットの手配)
- 旅行相談業務(有料の場合)
3.事業としていること
- 登録制度(幹事がお宿から謝礼をもらったなどは事業に該当しない。)
- 旅行業を営むためには、旅行業の登録が必要になる。
※次項の旅行業法「登録」で詳しく解説しています。
旅行業の種類
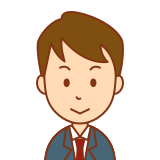
旅行業は以下のように分類されます。例えば「旅行業者」「旅行業者等」はよく設問に出てきますので、違いをしっかりと意識して設問を回答していきましょう。
1.旅行業
旅行業は、以下の4種類。
- 第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業
2.旅行業等
旅行業を含めた全体的な言い方。
※「旅行業者代理業」は旅行業ではない。
- 旅行業者、旅行業者代理業
3.旅行サービス手配業
旅行業者のために、旅行業者とサービス提供者の間に入り、各種サービスの手配を行う。
※「旅行サービス手配業」は旅行業ではない。
旅行業に該当しないもの
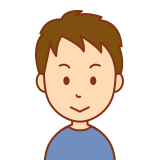
「旅行業とは」「旅行業の種類」について説明しましたので、次に「何が旅行業等の業務に該当するのか、しないのか」についてみていきます。ここでは、「旅行業等に該当しないもの」について考えてみましょう。
1.添乗員派遣業者、渡航手配代行業者(ランドオペレーター)
旅行業者等間の取引であり、直接旅行者の間に立っていない。
- ツアーコンダクターや通訳ガイド等を派遣する業者(旅行業者等からの依頼⇨間接的)
- パスポートやビザの取得を代行する業者(旅行業者等からの依頼⇨間接的)
2.運送または宿泊業者が自らの業務範囲内で自らサービスを提供する行為
- 運送業者(交通機関)が自社の機関を利用した日帰り旅行(宿泊を付けるには登録が必要なので当然に日帰りになる)
- 旅館やホテルが自社の宿泊施設を利用した宿泊サービ行為 (「自社の宿泊施設を利用した」というところがポイント) ex. スキー場を敷地内に経営するホテルで、旅行業の登録なしにリフト券付き宿泊プランを販売する。
3.運送や宿泊以外の旅行サービス(付随したサービス)を手配する業務
- コンサートチケットを販売するプレイガイド(企画旅行、手配旅行などの旅行になっていない)
- 添乗、通訳など、旅行者への案内(旅行業者との契約である⇨間接的)
4.もっぱら運送機関の代理発券業務を行う場合
- コンビニや埠頭でバスや船のチケットを売る行為
※運送機関ではない他社が販売・手配をする行為であるので登録が必要のように思えるが、「もっぱら(専ら、それだけを専門に)」運送機関の代理発券業務を行う場合に限り旅行業等の登録は不要とされている。
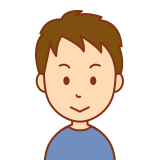
旅行業法「定義」はどのテキストを読んでもなんとなくピンとこない部分があります。実際に出題される問題を使って覚えるのが一番です。「確認テスト」にたくさん◯✕クイズを用意しましたので、何度も繰り返して覚えていきましょう。
確認テスト

確認テスト 旅行業法「定義」
PLAY AGAIN を押すと、新しい問題がランダムに出題されます。何度も違う問題に挑戦しましょう。